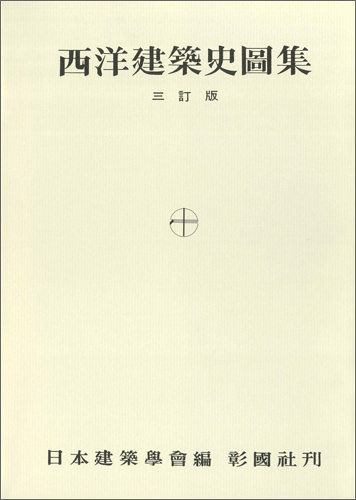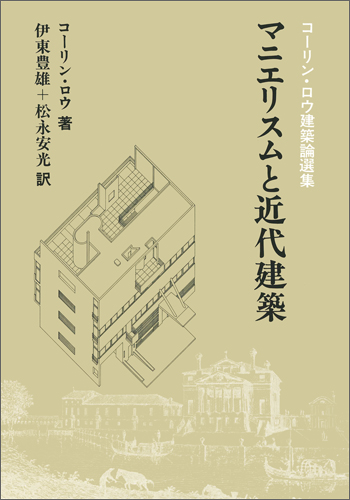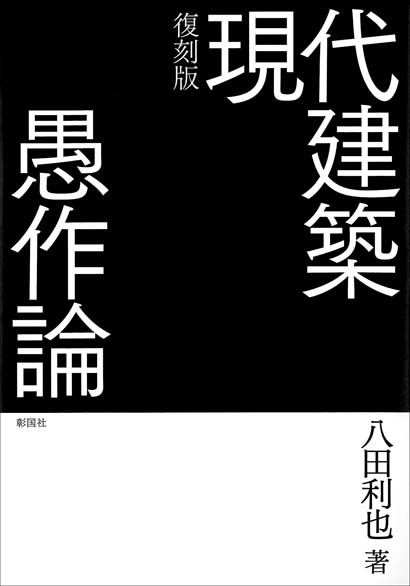- 本・雑誌案内
五十嵐太郎 読み継ぐべきこの3冊
建築史を専門とする人以外も、歴史を学んでほしいと思っています。教科書的なもの、歴史の流れに近代建築を位置づける視点をもたらすもの、現代建築を批評しながら、日本建築史の知見も取り込んだもの。どの本にも「歴史」が含まれているんです。
西洋建築史図集 三訂版
豊富な写真と図面、解説。情報量と網羅性がすごい!
この本は、教科書として知られていますが、旅行に図面と解説をコピーして持っていったり、いろいろな使い方が考えられます。僕は、大学院の試験で後ろの解説を2回通して読んで合格したんです。写真は白黒ですが、解説に欧文の名称も表記してあるので、画像検索と併用した、ハイブリッドな使い方がお勧めです。良い解説にはネットからはなかなかたどり着けません。現時点でこれを超えるものはないでしょう。
西洋建築史図集 三訂版
日本建築学会 編
西洋建築史教材の定番。日本建築学会が毎回大幅な改訂を重ね、この三訂版では、収録図版総数は800余点、解説は120頁を越える。この本の特色は、できるかぎり多くの図版を収録し、それぞれの図版に必要最小限の解説をつけた点にある。
>購入する
>購入する
コーリン・ロウ建築論選集 マニエリスムと近代建築
西洋古典建築と近代建築を接続するアクロバティックな形態分析!
いまは、西洋の古典建築への関心は薄くなっているかもしれません。でも、本書の、近現代の建築を大きな歴史のなかに位置づける見方や形態分析は、西洋建築史の教養があればこそできるもの。かつてはデザインをやる人も歴史が重要という認識がありましたが、いまは消えてしまっています。この本の「建築の形」そのものを見る見方は、「形」を読み解く基礎として、いまの建築を見るうえでも、ヒントになります。有名な「透明性 虚と実」の論は、概念的に建築を分析する方法を提示して、創作をするひとにも刺激を与えると思います。本に図版がない建築も現在はネットで検索でき、読みやすい環境となっているので、ぜひ挑戦してほしいと思います。
コーリン・ロウ建築論選集 マニエリスムと近代建築
コーリン・ロウ 著/伊東豊雄・松永安光 訳
巻頭の論文「理想的ヴィラの数学」でロウはコルビュジエとパラディオの建築の類似性を極めて数学的に証明し、さらに究極的には両者ともヨーロッパの伝統に深く根ざしていると察する。これと次の論文「マニエリスムと近代建築」により、ロウは若き建築家たちに、現代建築に生命を吹き込むための新しい手法を教示した。ほかに「固有性と構成」「シカゴフレーム」「新『古典』主義と近代建築Ⅰ・Ⅱ」「透明性」「ユートピアの建築」「ラ・トゥーレット」を収録。
>購入する
>購入する
復刻版 現代建築愚作論
一見言いたい放題の辛口批評。実は専門領域フル活用の現代的集合知。
磯崎新、伊藤ていじ、川上秀光が、共同のペンネームで書いた建築批評です。言いたい放題に人を食ったように見えますが、社会や建築のあり方や職能をめぐる鋭い批評、批判に満ちています。それぞれの専門領域をフルに活用した集合知でもあります。戦後のドラスティックな変化をめぐる証言としても、現代の建築の変化と重ね合わせても面白いのですが、何より皮肉やアイロニー、反語など、さまざまな語り口は魅力的です。いま、建築をめぐる議論は、SNSなど自由に広がっているようで、すぐ炎上したり、学生やメディアも批判を避けるようにおとなしくなってしまっています。こういう言説があることは重要ですね。
復刻版 現代建築愚作論
八田利也 著
はったりをきかせたペンネームの著者は、若き日の磯崎新、伊藤ていじ、川上秀光の3人。1961年の刊行以来、建築界に物議をかもした話題作をついに復刻。若手建築家、藤村龍至が「解説『量』から『アーキテクチャ』へ」を解題。「建築家を取り巻く問題が1961年当時と2011年現在であまりにも似過ぎていて、そのまま読んで十分に説得力があり、しかも参考になる」と、本書の現代性を深く論及している。
>購入する
>購入する
五十嵐 太郎(いがらし たろう)
1967年、パリ生まれ。東京大学大学院修了。博士(工学)。現在、東北大学大学院教授。第64回芸術選奨文部科学大臣新人賞、2018年日本建築学会教育賞。ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー、あいちトリエンナーレ2013芸術監督。主な著書=『現代建築宣言文集[1960-2020]』(彰国社)、『建築の東京』(みすず書房)、『装飾をひもとく』(青幻舎)、『モダニズム崩壊後の建築』(青土社)、『新編 新宗教と巨大建築』(ちくま学芸文庫)、『建築と音楽』(NTT出版)ほか多数。*本記事は、彰国社90周年特別企画として公開された記事を転載したものです。